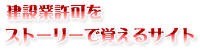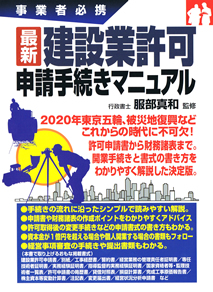工事の種類について
黒腹さんは専任技術者の要件について説明します。
専任技術者の要件
 「いよいよ、専任技術者の要件について説明しましょう。まずはこの表を見てください。」
「いよいよ、専任技術者の要件について説明しましょう。まずはこの表を見てください。」 一般建設業許可における専任技術者の要件 |
裏づけ資料 |
|
|---|---|---|
(a) |
指定された大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者 | 修業(卒業)証明書 + 実務経験確認資料 |
(b) |
指定された高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者 | 修業(卒業)証明書 + 実務経験確認資料 |
(c) |
10年以上の実務経験を有する者 | 実務経験確認資料 |
(d) |
一定の国家資格、免許等を有する者 | 資格認定証明書等 |
 「専任技術者の要件って、一つではないんですね・・・。」
「専任技術者の要件って、一つではないんですね・・・。」  「そうでなんです。この要件(a)、(b)、(c)、(d)のいずれかに該当すれば、専任技術者の要件をクリアできます。それぞれの詳細は文字をクリックしてください。」
「そうでなんです。この要件(a)、(b)、(c)、(d)のいずれかに該当すれば、専任技術者の要件をクリアできます。それぞれの詳細は文字をクリックしてください。」  「オイラは(d)でクリアできるんっすね~!」
「オイラは(d)でクリアできるんっすね~!」  「その通りです。ただし、これ以外にひとつの営業所に常勤しているという要件も満たさなくてはいけません。」
「その通りです。ただし、これ以外にひとつの営業所に常勤しているという要件も満たさなくてはいけません。」  「常勤って言っても、具体的にはどのような状況でないといけないんですか?」
「常勤って言っても、具体的にはどのような状況でないといけないんですか?」  「一般的に考えられるフルタイム勤務ということになりますが、逆にこういう勤務は認められにくいというケースを挙げると『(1)住所が営業所の所在地から著しく遠距離で、常識上通勤不可能と考えられる場合』、『(2)他の営業所や事業に専任しないといけない者』、『(3)他の事業、法人の経営者、役員等』ですね。」
「一般的に考えられるフルタイム勤務ということになりますが、逆にこういう勤務は認められにくいというケースを挙げると『(1)住所が営業所の所在地から著しく遠距離で、常識上通勤不可能と考えられる場合』、『(2)他の営業所や事業に専任しないといけない者』、『(3)他の事業、法人の経営者、役員等』ですね。」  「(2)がちょっとイメージしにくいんですが・・・」
「(2)がちょっとイメージしにくいんですが・・・」  「同一事業者の元で、他の営業所の専任技術者となっている者は当然ですが、他にも事業者が他の法律、例えば「建築士」や「宅地建物取引主任者」などの登録をしていると、他の法律の義務により、専任義務を要している者がいる場合があるんです。」
「同一事業者の元で、他の営業所の専任技術者となっている者は当然ですが、他にも事業者が他の法律、例えば「建築士」や「宅地建物取引主任者」などの登録をしていると、他の法律の義務により、専任義務を要している者がいる場合があるんです。」  「実務経験っていうと、どういう経験までが認められるんすか?」
「実務経験っていうと、どういう経験までが認められるんすか?」  「この場合の実務経験というのは、雑務を除く建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。設計技術者としての設計や、現場監督技術者としての監督、作業員またはその見習いなどの経験なども含まれます。」
「この場合の実務経験というのは、雑務を除く建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。設計技術者としての設計や、現場監督技術者としての監督、作業員またはその見習いなどの経験なども含まれます。」  「ということは、俺の場合だと猿田建設で見習いをやっていたものや、作業員として働いていたものとかもすべて含まれるのか・・・。独立後のものを含めると全部で17年近くありますね・・・。」
「ということは、俺の場合だと猿田建設で見習いをやっていたものや、作業員として働いていたものとかもすべて含まれるのか・・・。独立後のものを含めると全部で17年近くありますね・・・。」  「ちなみに学歴はどうですか?」
「ちなみに学歴はどうですか?」  「高卒です。月の輪工業高校土木科を出ました。」
「高卒です。月の輪工業高校土木科を出ました。」  「いいですね~。それだと実務経験は5年で構いませんから、3工種の許可を受けることができますよ。」
「いいですね~。それだと実務経験は5年で構いませんから、3工種の許可を受けることができますよ。」  「ということは、実務経験の期間って重複しては認められないんですか?」
「ということは、実務経験の期間って重複しては認められないんですか?」  「そうなんですよ。少しおかしな話なんですが・・・。」
「そうなんですよ。少しおかしな話なんですが・・・。」  「小太郎くんは土木科だったから良かったけど、それなら資格も建設業関係の学歴もない場合、10年も実務経験いるし、せいぜい1工種の許可を得るのが精一杯なんじゃない?」
「小太郎くんは土木科だったから良かったけど、それなら資格も建設業関係の学歴もない場合、10年も実務経験いるし、せいぜい1工種の許可を得るのが精一杯なんじゃない?」  「そういうケースも結構あるので、実務経験10年で考えるしかない場合は、実務経験の要件緩和というものが認められる場合があります。」
「そういうケースも結構あるので、実務経験10年で考えるしかない場合は、実務経験の要件緩和というものが認められる場合があります。」 実務経験の緩和が認められる工種 |
|---|
●とび・土木・コンクリート・しゅんせつ ●水道施設工事 ●屋根工事 ●ガラス工事 ●防水工事 ●熱絶縁工事 ●大工工事 ●内装仕上げ工事 |
専任技術者として 担当する工種 |
担当工種 経験年数 |
振り替えられる工種 |
振り替える工種 必要経験年数 |
|---|---|---|---|
とび・土工、しゅんせつ、水道施設 |
8年 |
土木一式 |
4年以上 |
大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 |
8年 |
建築一式 |
4年以上 |
大工 |
8年 |
内装仕上げ |
4年以上 |
内装仕上 |
8年 |
大工 |
4年以上 |
 「なるほどな~。」
「なるほどな~。」  「ずっと気になってたのは、専任技術者の要件表にある『裏付け資料』という項目ね・・・。」
「ずっと気になってたのは、専任技術者の要件表にある『裏付け資料』という項目ね・・・。」  「また、お役所のハンパねー、確認っすか?」
「また、お役所のハンパねー、確認っすか?」  「ハハハ・・・。その通りです。当然、学歴や資格、実務経験もきちんと証明しなくてはいけませんよ・・・。」
「ハハハ・・・。その通りです。当然、学歴や資格、実務経験もきちんと証明しなくてはいけませんよ・・・。」  「特に実務経験の確認資料っていうのが、ハッキリ書いてませんよね?」
「特に実務経験の確認資料っていうのが、ハッキリ書いてませんよね?」  「実務経験は、その工事に携わっていたことを証明する必要がありますので、証明したい工事の種類に関して『工事請負契約書』を掲示する必要があります。」
「実務経験は、その工事に携わっていたことを証明する必要がありますので、証明したい工事の種類に関して『工事請負契約書』を掲示する必要があります。」  「え~!そうなんですか!? でも、工事を請ける時にいちいちそんなもの作ってませんよ・・・。」
「え~!そうなんですか!? でも、工事を請ける時にいちいちそんなもの作ってませんよ・・・。」  「う~ん。本来は契約書を作らないといけません。ただし、個人事業などは特に契約書を作っていない場合はありますから、代わりに『注文書』と『請書』をセットにしたもので構いません。」
「う~ん。本来は契約書を作らないといけません。ただし、個人事業などは特に契約書を作っていない場合はありますから、代わりに『注文書』と『請書』をセットにしたもので構いません。」  「う・・・。それすら作ってませんでした・・・。スイマセン・・・。」
「う・・・。それすら作ってませんでした・・・。スイマセン・・・。」  「まー、それもよくあります・・・(苦笑)。最終手段は『請求書』と『領収書、または振込みの確認できる通帳』です。これはどうですか?」
「まー、それもよくあります・・・(苦笑)。最終手段は『請求書』と『領収書、または振込みの確認できる通帳』です。これはどうですか?」  「あ、あります!あります!それは、さすがに無いと取引できませんし・・・。」
「あ、あります!あります!それは、さすがに無いと取引できませんし・・・。」  「ただし、この場合は信憑性の問題もありますので、取引相手に『発注証明書』の署名と押印をお願いする必要があります。」
「ただし、この場合は信憑性の問題もありますので、取引相手に『発注証明書』の署名と押印をお願いする必要があります。」  「それは、どんな書類ですか?」
「それは、どんな書類ですか?」  「簡単に言うと、掲示する予定の『請求書』と『領収書、または振込みの確認できる通帳』について、自分が発注した工事のもので、間違いないですよ。ということを具体的な工事内容とともに証明してもらうものです。任意の書式で構いません。」
「簡単に言うと、掲示する予定の『請求書』と『領収書、または振込みの確認できる通帳』について、自分が発注した工事のもので、間違いないですよ。ということを具体的な工事内容とともに証明してもらうものです。任意の書式で構いません。」  「くぅ~!めんどくせーっ! 兄さん、次からはちゃんと契約書交わしましょうぜ・・・」
「くぅ~!めんどくせーっ! 兄さん、次からはちゃんと契約書交わしましょうぜ・・・」  「俺も、それ思ったわ・・・(笑)」
「俺も、それ思ったわ・・・(笑)」 このページのまとめ
専任技術者の要件
- 専任技術者の要件は、資格や学歴と実務経験が基本。
- 他に、営業所への常勤性が求められる。
- 実務経験とは、設計技術者としての設計や、現場監督技術者としての監督、作業員またはその見習いなどの経験
- 実務経験の期間は工種ごとだが、重複はできない。
- ただし、実務経験10年で取得する場合、例外的に実務経験の緩和というものがある。
- 裏づけ資料は必ず必要
- 実務経験の裏づけ資料は『工事請負契約書』、『注文書と請書のセット』、『請求書と通帳・領収書に加え発注証明書のセット』など